「THE BIG ISSUE」vol.386に掲載されていた、小説家・小山田浩子さんのインタビューが面白かった。
編集プロダクションに勤められていた時のことが綴られていたのだが、取材して書いた原稿を先輩に見せたところ、「余計な情報が多すぎる」と言われたのだという。
たとえば記事に、イベントに参加した男の子のコメントを入れるとします。
「THE BIG ISSUE」vol.386
「〇〇で楽しかったです」と一言入れればいいところ、「ええっと……(と言い淀んでから母親の様子をうかがい、促されて)楽しかった……です」みたいな書き方になってしまう。
「楽しかった」だけではまとめきれない感情とかその場の雰囲気なんかを入れたくなってしまうんです。
何度も注意されるも、小山田さんの文章はなかなか直らない。そこで先輩が皮肉交じりに「こういう文章を書きたいのなら、小説家になればいい」と言ったところ、その言葉を真に受け、小説家を目指すようになったそうだ。
場所が変われば価値も変わる
小山田さんが担当していた情報誌では「余計な情報」と捉えられる文章が、小説を書くときはとても大切だったりする。場所を変えれば価値も変わるという好例だと思った。
実は私も編プロに入社したばかりの頃、まったく同じセリフを言われた。原稿にとにかく余計な情報(私は余計だと思っていないのだが)を入れてしまい、先輩から何度も赤字を入れられた。
実用書の編集者だったため、より簡潔に書くことを心掛けなければいけなかったのだが、入社するまで小説を読んでばかりだったこともあり、どうしても小説のような細かい描写を好んでしまっていたのだった。

ちなみに私は、ライターや編集者として生計を立てたいと考えていたので、余計と思われる情報を排除するトレーニングをたくさん行った。一時は簡潔な文章を心掛けすぎて、大好きな小説が読めなくなってしまったときもあったほど……あの時は辛かった……
今は簡潔な原稿を書きつつ、小説の文章も元通り楽しく読めるようになった。文章の使い分けができるようになったことは、トレーニングして良かったなと感じる。
同じ言葉を言われたとしても、考え方によって進む道は大きく異なる。そんなこともまた、しみじみと思うインタビューであった。
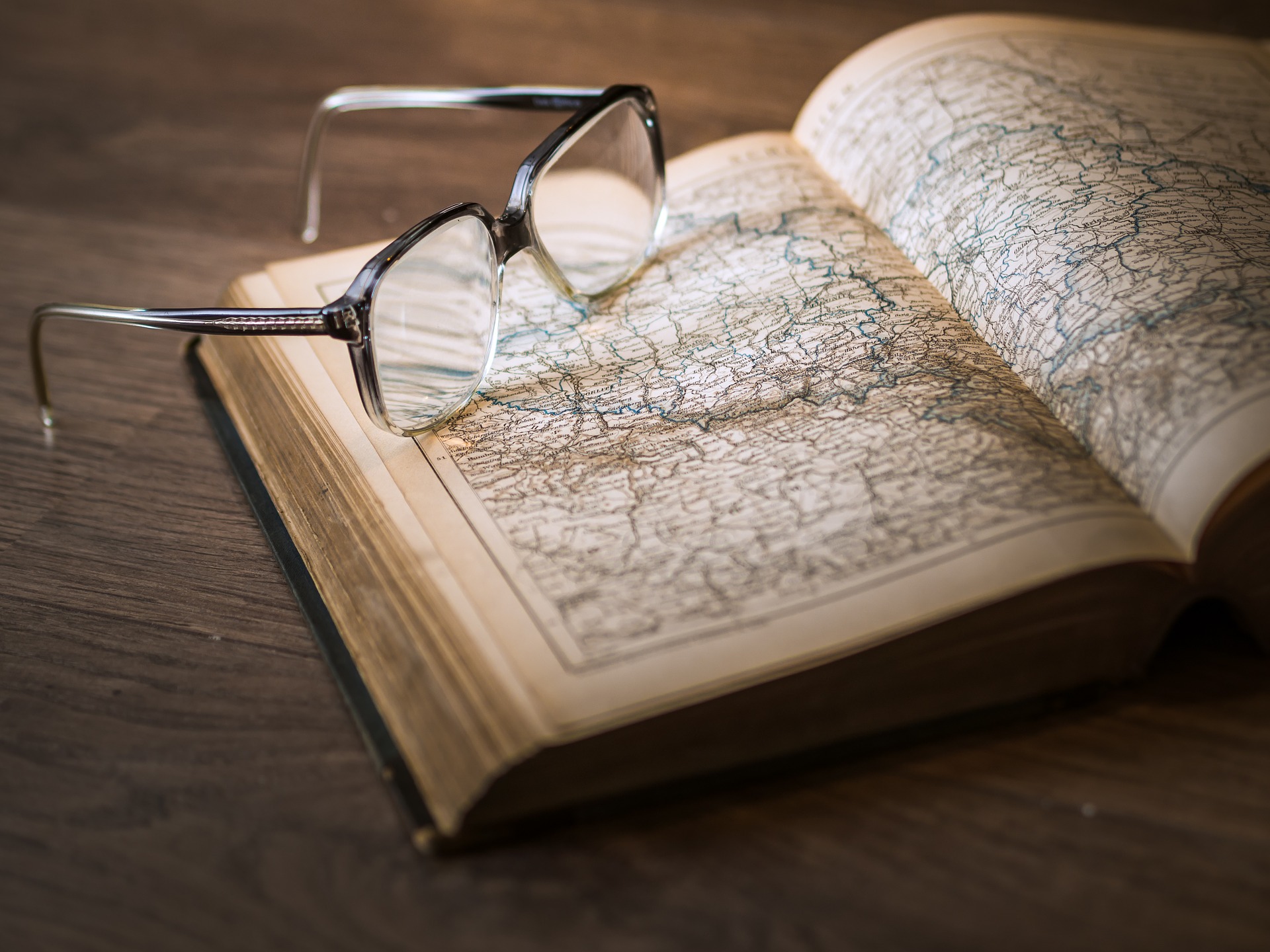

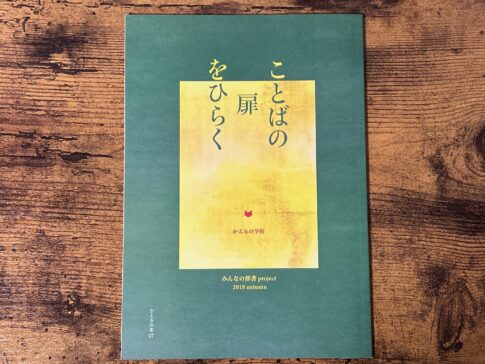





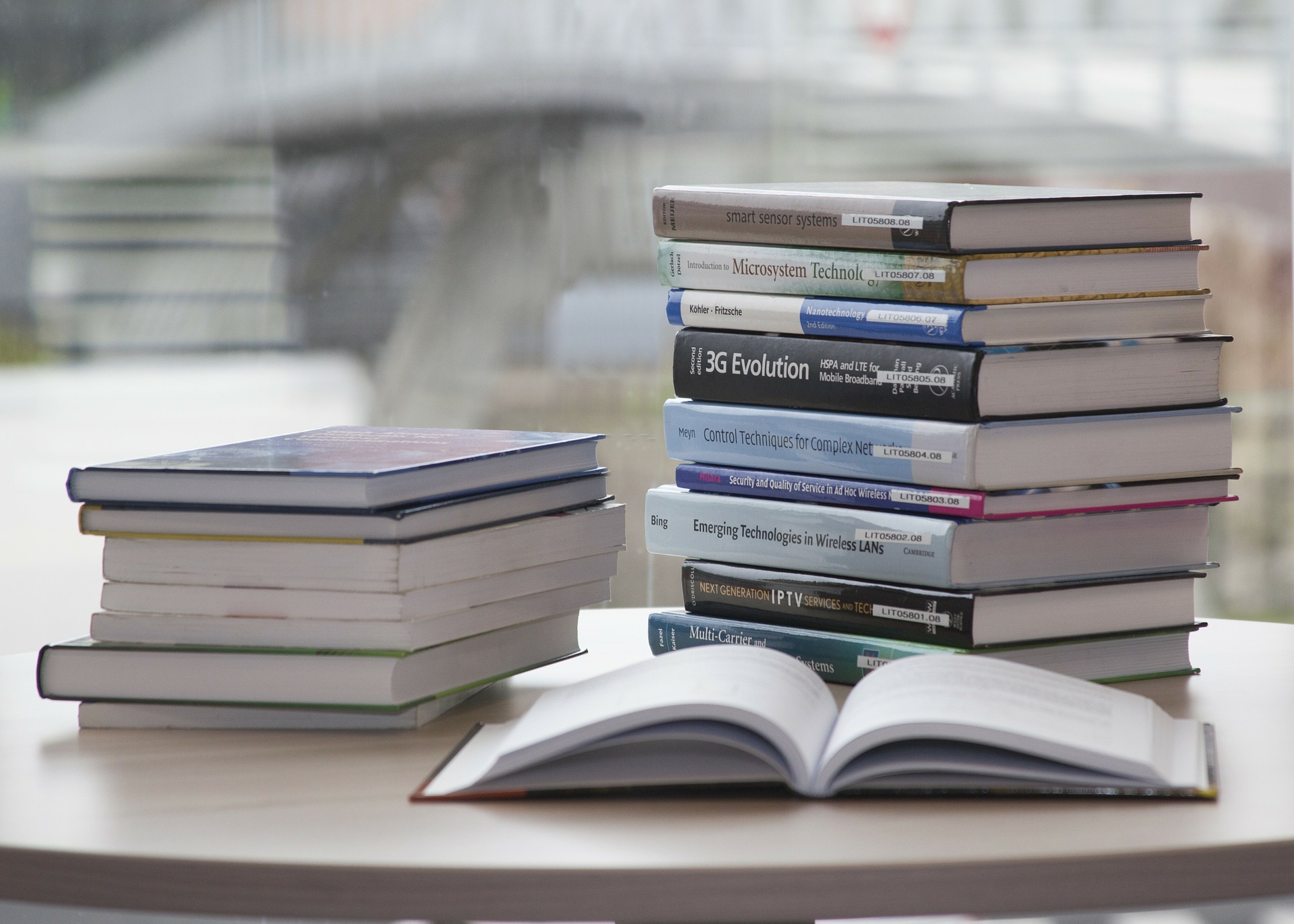



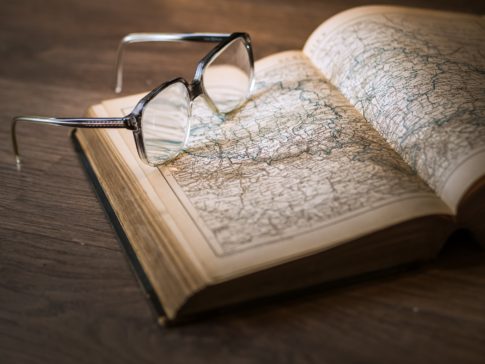

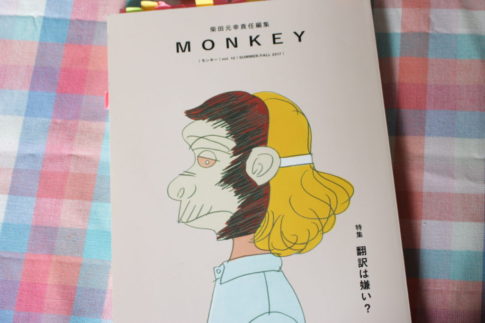
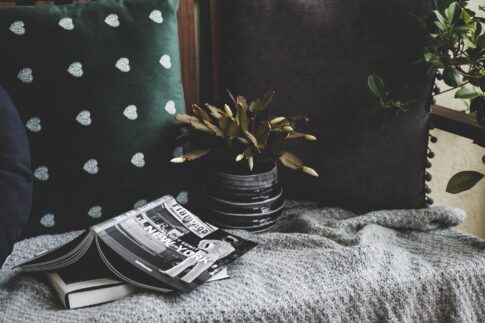
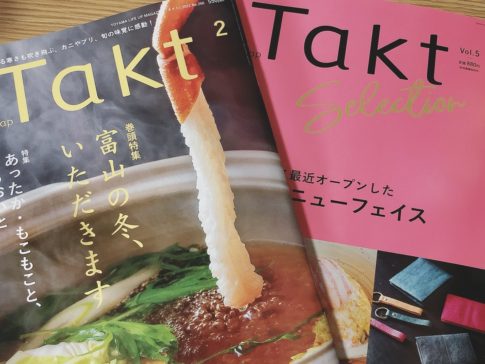





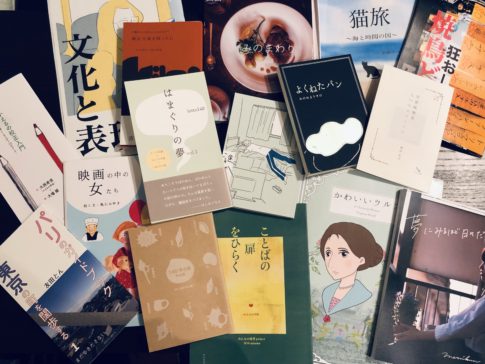


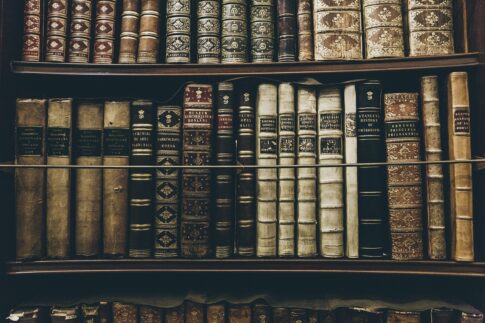




コメントを残す