はじめて村上春樹さんの翻訳を読んだのはおそらく、トルーマン・カポーティの『ティファニーで朝食を』。“小説家が訳す翻訳作品”というものを読むのも、初体験だった。
その後、同じく彼が訳したレイモンド・チャンドラーやスコット・F・フィッツジェラルド、J・D・サリンジャーなどの翻訳作品を読み漁った。私がアメリカ文学の面白さと出会えたのは、村上さんのおかげである。
そんな彼の翻訳スタイルや作品が事細かに記された『村上春樹翻訳ほとんど全仕事』。これまで読んだ作品について、そしてまだ出会っていない翻訳作品に出合いたく、本書を手に取った。
翻訳作品は100冊近く? 過去作品がずらり
本書の前半は、これまでに翻訳された作品がずらりと掲載されていた。村上さんの翻訳は結構読んでいたつもりだったが、本書を見るに、まだまだ読み切れていないことがよくわかった……
パラパラとめくった時点で唖然とする。厳密には数えていないが、ざっと100冊ほどではあるまいか。そして、“ほとんど”ということはたぶん、掲載されていない作品もあるのだろう(雑誌掲載のみで書籍化していないものもありそうでは)。
本書によれば、村上さんは計36年も翻訳家としての活動をされているそうだ。そうなると年に2~3冊は翻訳本を出していることになる。
自身の作品はもちろん、エッセイや『村上さんのところ』のような読者との対話、河合隼雄さんや柴田元幸さん、川上未映子さんらとの対談本も出ているし、その中でこの冊数は、どうこなしているのか見当もつかない。
掲載されていた翻訳作品の中から、未読の気になる作品をいくつかピックアップしてみる。
『マイ・ロスト・シティ』 スコット・F・フィッツジェラルド
村上さんの翻訳のきっかけは、フィッツジェラルドだったそうだ。とにかく、フィッツジェラルドを訳したくてはじめたと、本書に書いてあった。『グレート・ギャツビー』などは読んでいるけれど、これは未読なのでとても気になる。
『偉大なるデスリフ』 C.D.B.ブライアン
ギャツビーのオマージュとして書かれた一作だそう。「僕が訳さなければ誰も訳さないだろうなと思った」と村上さん。貴重な作品である。
『心臓を貫かれて』 マイケル・ギルモア
なんと奥様のリクエストで訳したのだとか。マイケル・ギルモアが、連続殺人犯で死刑になった実兄について書いた作品。題材はダークだけれど、実弟が書いているというところも興味深い。
小説執筆と翻訳が相乗効果を生んでいる
後半には柴田元幸さんとの対談が掲載されており、翻訳に対する思いや作業のスタンスなどがたっぷりと語られていた。印象的だったのは、村上さんが翻訳自体を純粋に、かなり楽しんでいるということ。
翻訳をしていると、いろんな新しい体験ができるし、文章の勉強になるし、頭の訓練にもなるし、たぶんそれなりに形になって残るだろうし、おまけに一応はお金になるし、なにしろいいことだらけです。……世の中にこんなに楽しいことはないですよ、ほんとに。
『村上春樹翻訳ほとんど全仕事』より
小説を生みだすとはまた違った脳を使っているのだろうな、とは思っていたが、確かにほかの作家の文章を別の形で言語化することは、「文章の勉強」や「頭の訓練」に繋がるのだろう。
そしてそれは、小説に還元されていくはずである。文体を学んだのは翻訳からだともいっていて、村上さんの小説は翻訳なくしてはありえないとも取れる。

また、村上さんは、小説を書くことに疲れたら翻訳をするという効率の良いスタイルで作業を進めているという。
そういう風に自分の創作と、翻訳の仕事とを、長期にわたって交互にやってこられたのは、僕の精神性にとっておそらく健全なことだったんだろうなと推測する。自由に好きにやれることと、制約の中でベストを尽くさなくてはならないこと。どちらか一方だけの人生だったら、やはりちょっと疲れていたかもなと思わなくはない。
『村上春樹翻訳ほとんど全仕事』より
ただ好きだから、というだけでなく「健全」だからという理由は、かなりしっくりくる。翻訳と小説を両輪のようにして進んできたからこそ、たくさんの素敵な作品が生まれたのだろう。
村上さんの翻訳事情は前々から知りたいと思っていたので、この本を出してくれて本当に嬉しい。とても興味深い一冊だった。
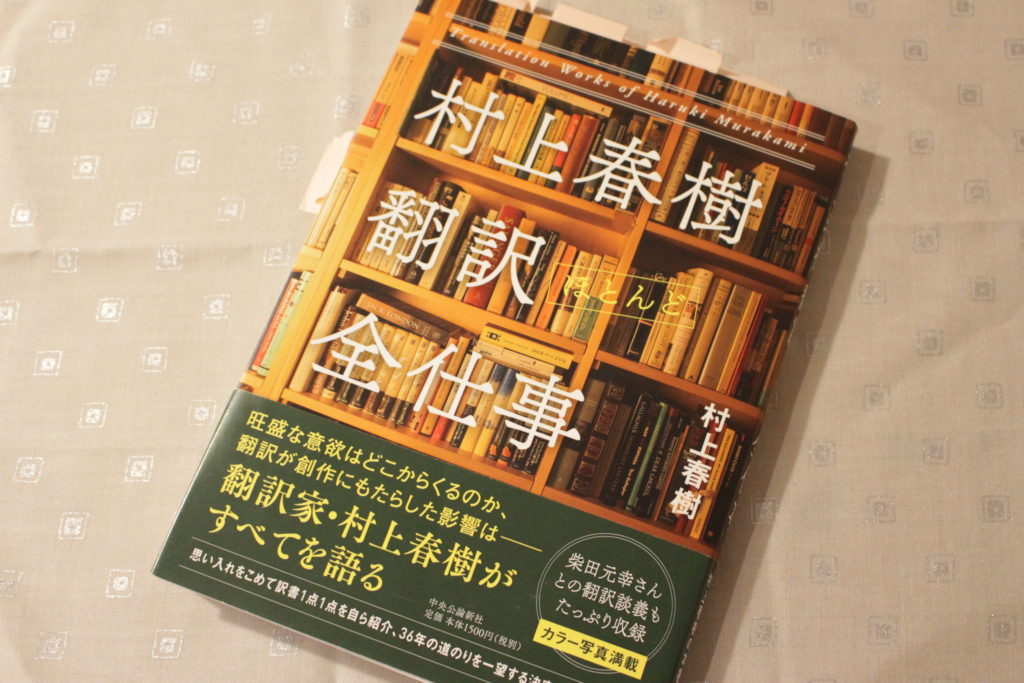


















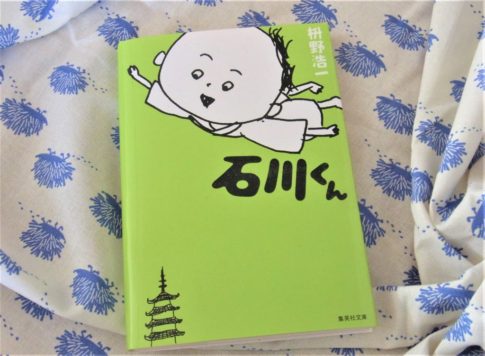



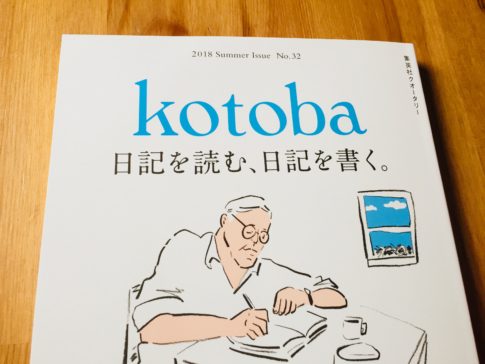






コメントを残す