「THE BIG ISSUE」vol.386の特集は「タネ、食の安全保障」。地域の固定酒や在来種のタネを守ろうと活動する人々を取材した記事がいくつか掲載されていた。その中で、15歳で伝統野菜のタネを流通する会社を起業したという小林宙さんのインタビューが印象的だった。
「タネから芽が出るときがおもしろい」とタネに関心を持ち、子どもの頃から親にねだっていたのは、ホームセンターの野菜のタネ。「同じ白菜でも『何が違うの?』っていうくらい種類がたくさんあった。おもしろそうだなと思って調べるようになったんです」と話す。
次第に、特定の地域で栽培される「伝統野菜」に関心を持つようになった。ところが伝統野菜のタネを探しに行くも、販売元の種苗(しゅびょう)店が廃業していたり、タネが途絶えたりしていることも多く、伝統が廃れていっていることを知る。
そこで、「タネを残すために何かできないか」と、会社設立に至ったという。
私たちはタネに支えられている
「世界からタネがなくなったら、人間は生きていけない」と小林さん。思えば米も野菜も果物も、その多くがタネからできている。さらに家畜を育てる飼料だって、元はタネ。私たちの生活は、タネに支えられているのだ。

「別に一つくらいタネの種類がなくなっても何とかなる」と思う人もいるかもしれないが、タネを一つ減らすことは可能性を一つ減らすことになる。
「伝染病が広がったり、気候が変わったりした時に、同じ品種の作物しか植えていなければ全滅して食べるものがなくなるかもしれない」と小林さんは語る。多様なタネを残すことは選択肢を広げるだけでなく、人類の生存戦略の一つでもあるといえる。
この記事を読むまで、恥ずかしながらタネのことなどまったく気にせず生きてきてしまった。しかし今はタネを残す大切さを知れたのはもちろん、単純にタネの面白さにも気づくことができた。小林さんの著書『タネの未来』もぜひ、読んでみたいところである。





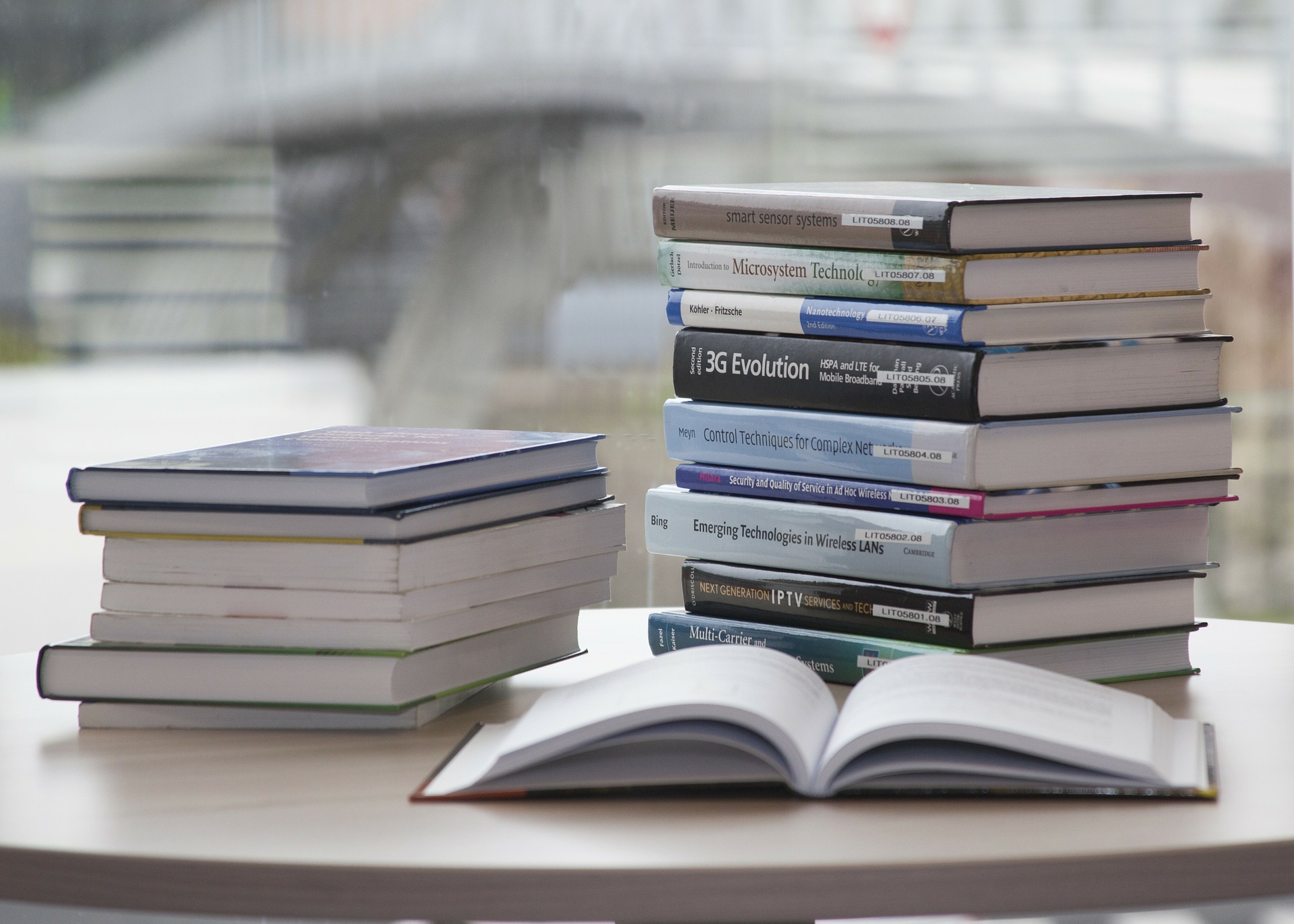




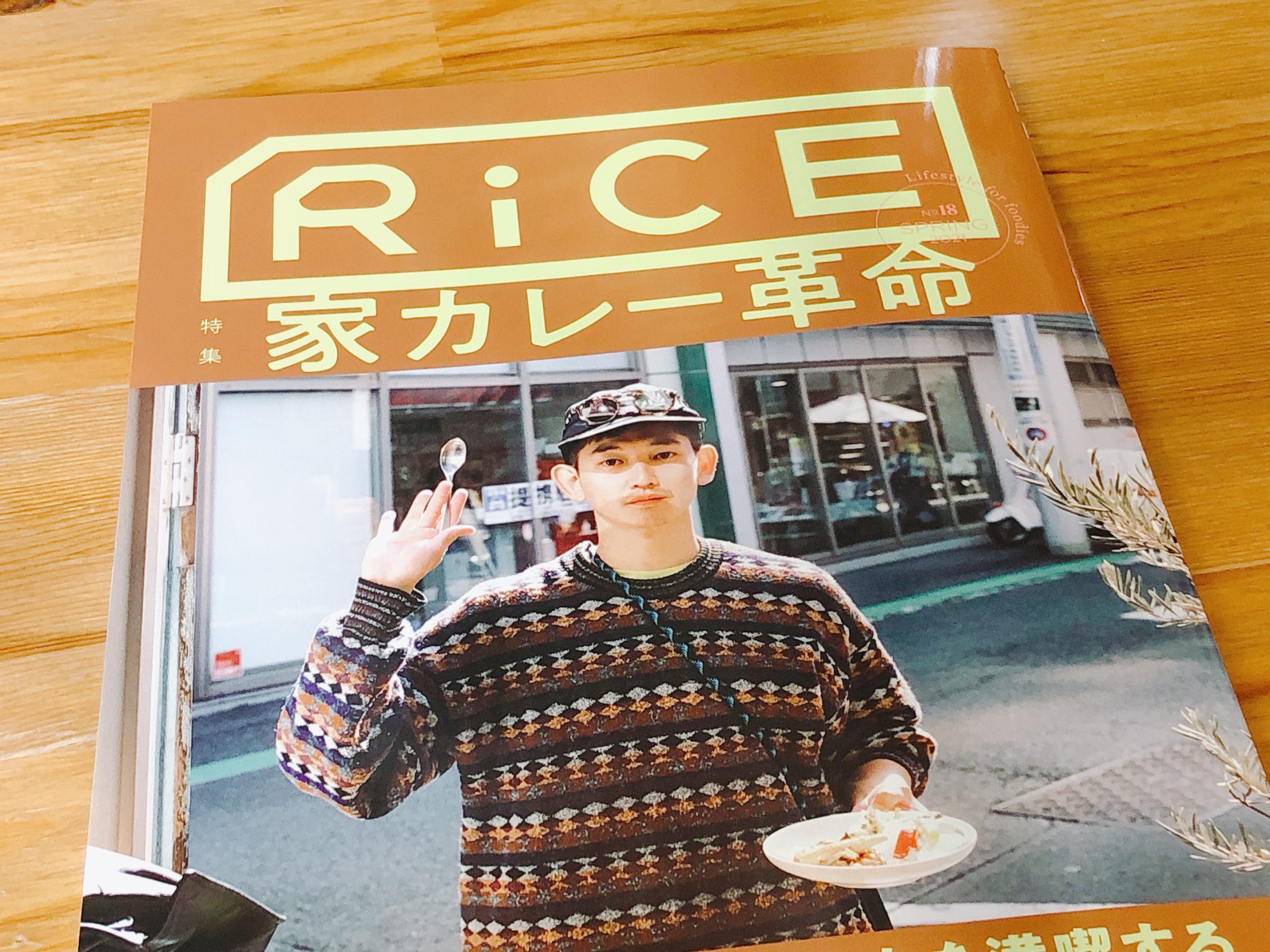



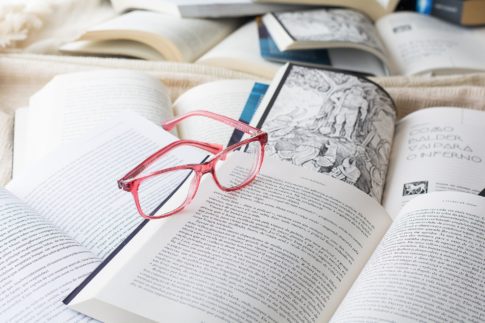

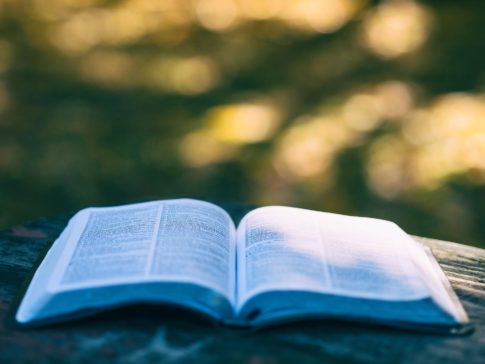
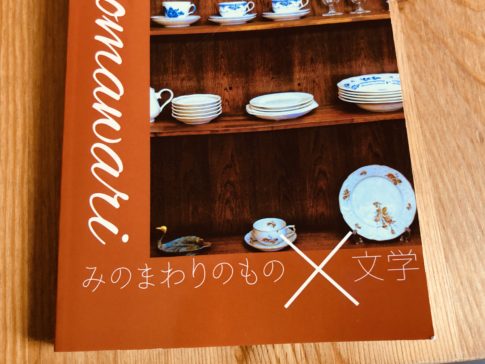






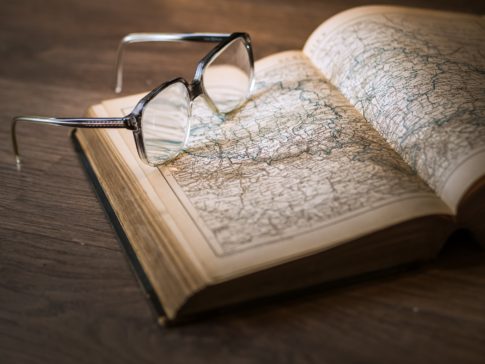

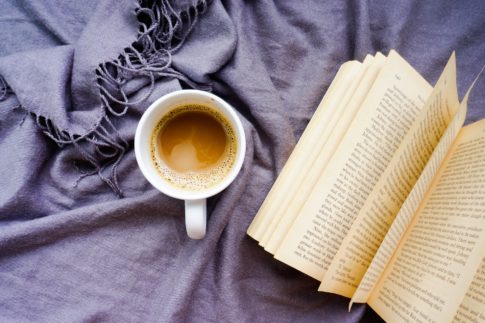
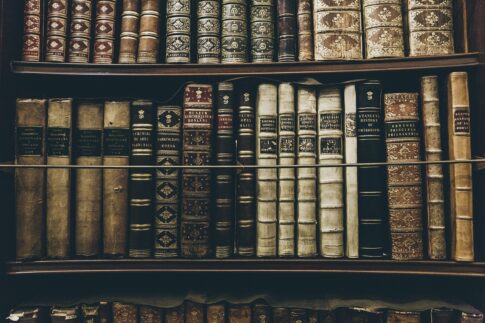




コメントを残す