吉本ばななさんの小説『彼女について』は「魔術」「呪い」「宗教」などの目に見えないものがキーワードとなっている。目に見えないものを信じること自体はもちろん悪ではない。しかし、それに振り回され、苦しみ、悲しい事件が巻き起こっていく様は、心が痛む。最近のニュースにも当てはまるような展開もあり、タイムリーであることが一層辛く感じたのかもしれない。
あらすじ、主人公・由美子の強さと儚さ
主人公・由美子の母と昇一の母は姉妹で、二人とも「特殊な宗教みたいなもの」の教祖の娘であった。ところが母たちの生き方は真逆。由美子の母は宗教に囚われ、いかがわしい商売にも手を出し、やがて事件を起こし、亡くなってしまう。一方の昇一の母はそれらと縁を切り、昇一を守り、宗教とは関係のないところで暮らしてきた。
母たちの真逆の生き方に従うようにして、由美子と昇一もまた、真逆の人生を歩んできた。家族や自分を傷つける母との関係に苦しんできた由美子と、宗教とは無関係に明るく楽しく暮らしてきた昇一。その対比が、物語ではときに鋭く描かれる。
そんな二人が母との縁の場所を巡っていく。その中で由美子は自分や母の過去と向き合い、自分にかかった呪いについて考え、自分自身を解放していくのである。

物語の中で由美子は強く、自分の意思をしっかりと持った人物のように思える。自分の心は誰にも奪えないということが、あちこちで書かれている。
見上げると光を反射しながらうろこ雲がまるで生き物みたいに波打って遠くまで続いていて、こういうものを見るときはこれから先のいつでも気持ちは同じに違いない、私からこういうきれいなものを奪うことだけはだれもできない。まるで決心をするように私はそう思った。
『彼女について』(文春文庫)p.10
そんな由美子でも母にかけられた「呪い」に苦しみ、恐怖を覚えている。ふいに自分が受けたショックの大きさを思い知り、何度も自分で自分を慰めている。そのシーンは優しく描かれているものの、やはり読んでいて心が苦しくなる。振り返ってみれば、彼女は強い意志を持っていたのではなく、つねに持とうと意識していたのかもしれないと思う。
自分を取り戻していく由美子には、本当にほっとする。由美子以外にも宗教の騒動に巻き込まれ、辛い思いをした後に立ち上がっている人々も登場し、心を痛めながらも勇気づけられる作品となっていた。
昇一の存在が分断を生みつつも、救いとなっている
昇一と由美子はあまりに育ってきた環境が違うため、死生観や生きる上での感覚に大きな乖離がある。母からの呪いに苛まれて苦しむ由美子に対し、昇一は比較的まっすぐで、純粋なポジティブさがあり、これはときに二人の分断を分断するきっかけにもなっている。
私ははじめ、勝手に由美子の側についた気になって「昇一にはわからないよ!」と思ってしまいがちだったが、彼のその性格がときに由美子を救う手立てにもなっていることがわかり、それこそ私が何をわかっているのかと、反省したのであった。
例えば、由美子が冗談交じりに「じゃあ今すぐに結婚して、いっしょに良き家庭を作ってくれる?」と言うと、昇一はあっさり承諾する。自分が由美子を放っておいたせいでこんなことになってしまったと思うゆえに、結婚の約束もサクッとしてしまうのだ。その純粋さに救われるし、怒りたくもなるしで複雑だった。ただ、由美子のように弱ってしまっている人の近くには、昇一のように精神が歪まずまっすぐな人がそばにいることがわりと大事なのではとも感じた。
私は比較的抱え込みやすいので由美子に共感するが、確かに昇一のようなメンタルが健康な人がそばにいると、自分も穏やかになり解放されることがある。呪いを解くよりも「君がいい気分でいることのほうが、大事だと思う」という昇一が心強かった。

ちなみに、物語内では由美子の母がマインドコントロール下にあったことが記述されていて、彼女が犯した罪についても「しなくてはならないことだと思ってしてしまうところまで行ってしまっていた」のではないかと推測されている。由美子が被害者であることは間違いないが、母もまた被害者の一面があったことが苦しい。
後半の怒涛の展開は、夢なのか現実なのか定かでなく、それでいながら解放感があり、個人的には胸がいっぱいで涙が出た。ふわふわと不安や悲しみが漂う中に、一筋の光をしっかりと見据えるような物語だった。そして最後に、文庫版あとがきの「とにかく人生を最後まで生き抜きましょう!」という力強いメッセージを受けとり、私も頑張ろう、と励まされたのであった。






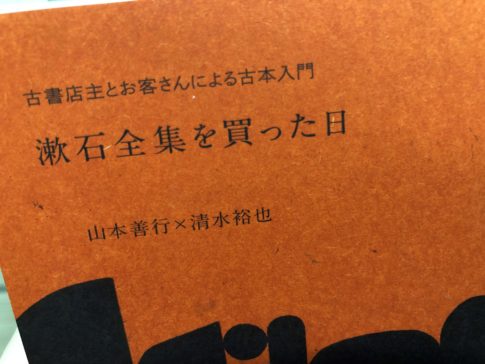
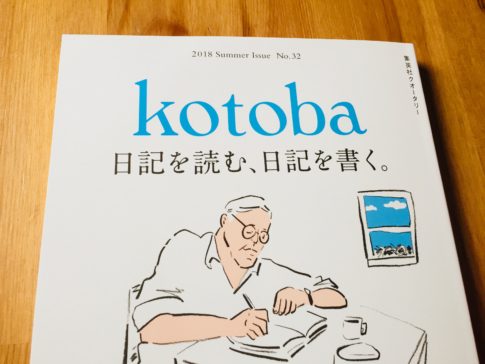
















コメントを残す