大学生の頃、イギリスへ行って聖地巡礼のように好きな作家の出身地や物語の舞台を歩き回った。イギリス文学オタクだった私は何もかもにテンションが上がって、立ち止まってはじんわり世界観に浸り、現地の空気を存分に吸った。
『清少納言を求めて、フィンランドから京都へ』の著者のミア・カンキマキさんもきっと、似た気持ちを味わったのではないかと推測する。同書はフィンランド人のカンキマキさんが日本を訪れ、清少納言の軌跡を辿るノンフィクション。日本作家のことなのに、いざ読んでみると知らないことばかりで驚いた。
読み終えた今、こう思っている。清少納言、なんてかっこいいの……彼女のことを、もっと知りたい。
清少納言と友達のように接する?
清少納言の『枕草子』を好きになったフィンランド人のミア・カンキマキさんは、あるとき日本に行って清少納言を研究しようと思い立つ。自分と清少納言は「驚くほど似ている」といい、自分を理解してくれる存在だと話す。
きっとあなたは私のことを理解してくれる気がする。私の友人だって、その多くがあなたのことを好きになるだろうし、あなたを友人と引きあわせれば、いっきに皆の人気者になるかもしれない。ランチ、女子会、週末コテージ、列車の旅、ブックフェア、シャンパンブランチなんかを開く人がいたら、そこに呼ばれるかもしれない。
『清少納言を求めて、フィンランドから京都へ』p.20~21
私にとって清少納言は歴史上の人物。似ているとか、自分をわかってくれるとか、そんなふうには考えたことがなかった。しかし確かに、本書を読んでいくうちに清少納言のユーモアやかわいらしさ、強さなどを知ることになり、徐々に近しい存在に感じられるようになった。
「あなたのユーモアは、キャリーやサマンサやミランダの時代にならないとわかってもらえないのね」(p.67)というカンキマキさんのコメントが好きだ。清少納言のユーモアはSATC的な一面があるように思う。教科書を読んだときは微塵もそんなことを思わなかったが、日常のテンションの上がることや、逆にムカついたことをつらつら述べている文章は、気軽なおしゃべりのようで楽しい。

清少納言について知っていること、知らないこと
学生の頃暗誦した『枕草子』。思い返せば私の清少納言の知識はそれくらいのものである。だから本書は私にとっても、彼女を知る旅のような一冊だった。
本書ではたびたび、清少納言がありとあらゆるものをリストアップしたという「ものづくしリスト」が登場する。好きなもの、嫌いなもの、木や山のこと、すべきこと、彼女はとにかくリストをたくさん作っているが、それが何を示しているのかは、未だによくわかっていないそうだ。
あなたのリストというのは、つまり、ただの何でもないリストではなく、思っているほど少なくとも単純でもない。その多くが変わっているので、訳本では翻訳されずに取り除かれているほど。研究者たちは、あなたのリストが何を意味しているのか、なぜあなたは列挙したのか、どこから着想したのかについて議論を交わしている――こういったリストは日本文学であなたの前にも後にもない。
『清少納言を求めて、フィンランドから京都へ』p.260
親しみやすく、さらっと読める形式であるからこそ、趣味だけでなく政治的な意見なども取り込むことができているという。何気ないものではあるが、万能な型なのだなあと感心する。

私はこういう、人のリストを見るのが好きだ。食べたものの羅列や、趣味の一覧、箇条書きになっているものは書いた人の個性が存分に出て面白い。自分で書くのは言わずもがな。カンキマキさんも気分が良くなることや読書リスト、買い物リストなどを作っているといい、リストは何か人を惹きつけるものがあるのだなとしみじみ思う。
清少納言は何か狙いがあったのだろうか。もしかして、何にもなかったりして。それでも面白いのだから、不思議である。
せっかく魅力を知れてきた一方で、清少納言にはかなり謎が多く、情報が少ないこともわかった。例えば清少納言という名は「清」という名字と「少納言」という役職名でできており、実名がわからない。宮仕えを辞めた後の消息もわからないし、研究書も紫式部に比べて圧倒的に少ないという。
カンキマキさんは博物館に日本語の解説しかなかったことを語っていたが、日本人の私が調べればもっとわかるのだろうか……もしそうだとしたら、海外にもっと門戸が開かれればよいのだけれど。
清少納言とフェミニズム
最も興味を惹かれたのは、清少納言がフェミニズム研究に取り上げられているという点だ。
中宮の周りに集まった三、四十人の宮廷女房たちが形成するサロンは、女たちのコミュニティ空間であり、ヴァージニア・ウルフがさぞや羨ましいと思ったであろう「自分たちだけの部屋」だった。彼女たちは自分たちの仮名文字の他に、女性らしい仮名による会話が繰り広げられる自分たちの空間を持っていた。
『清少納言を求めて、フィンランドから京都へ』p.72
ヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』はもちろん、読んだことがある。女性が文章を書こうと思うのであれば、お金と自分一人の部屋が必要であるという提言が有名な一冊であるが、それをすでに実践していたのが清少納言を含む、平安の女性作家たちなのだという。
実際、1990年代のフェミニズムの文学研究では平安時代の女性作家が取り上げられ、ジェンダー解釈がなされることも多かったそうだ。平安時代の作品が、今の私が考えていることと地続きになっているなんて、思いもしなかった。
私は日本に暮らしていて、清少納言についても学んだことがあって、作品も一部であれば今でも暗唱できる。それなのに彼女の魅力を全く知らなかったのが、なんだか悔しい。身近に感じた彼女のことを、もっと知りたい気持ちになった。








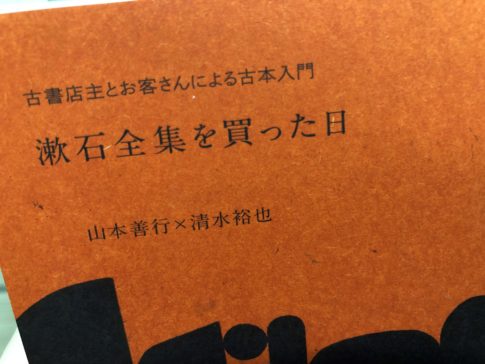

















コメントを残す