川上未映子さんが村上春樹さんにインタビューを行った『みみずくは黄昏に飛びたつ』。創作の裏側、小説家としての在り方、フェミニズムへの問いなど、かなり幅広い内容を深く、深く切り込んでいる。私が気になっていたことも聞いてくれていて、ありがたい一冊であった。
抽斗を作り、然るべき時に開ける
創作にまつわる話を読んでいると、「ぱっと思い浮かんだ」というような、感覚的な話が多く語られていた。例えば、『1Q84』の主人公・青豆の名前は、「名前をあれこれ考えているうちに、そういえば(安西)水丸さんと恵比寿で酒を飲んでた時の居酒屋のメニューで、青豆豆腐っていうのがあったよな、とふと頭に浮かんだ。で、よし、これでいこうぜと」(p.22)なんて言っているし、『騎士団長殺し』は「突然頭に浮かんだんです、ある日ふと」(p.73)と語っている。
村上作品に印象的な比喩表現さえも、感覚的なものを大切にしているゆえに「ぱっと出てこない時は、比喩は使わない。無理に作ろうとすると、言葉に勢いがなくなっちゃうから」(p.23)と言う。
これはある種の才能、センスという部分はあるだろうけれど、個人的にはこの感覚はおそらく、ふだんの生活で培われたものではないかと感じた。音楽や本や映画、彼が目にするものからのたくさんのインプットが関係しているのではないか。
実際、「作家にとって必要なのは抽斗なんです。必要なときに必要な抽斗がさっと開いてくれないと、小説は書けません」(p.126)と語っていて、ふだんからの意識した抽斗作りが「ふと浮かぶ」に繋がっているような気がする。
川上さんは村上作品について「内的な読書」というニュアンスが強いと言っていたが、それもまた、この抽斗作りに関係があるような気がする。彼の内にあるものから作られている物語だと感じるだからこそ、私たち読者もまた、自分の中にあるものと併せて読む。川上さんが言う、「そこに行けば大事な場所に戻ることができる、みたいな感じ」(p.33)を、私も村上作品に強く感じている。
文体を進化させ続けること
私が村上作品で最も好きなところは、「読み心地の良さ」である。村上さんの本を読み始めたあたりから、何となくほかの作品でも読み心地の良さを重視する傾向があり、物語の展開よりも文章が素晴らしいかどうかのほうに注目してしまう。
本書では、文体に関する話も語られていてとても嬉しかった。村上さんは小説家人生の中でやってきたことは、「文体を作ること、ほとんどそれだけ」だといい、「とにかく文章を少しでも上手なものにすること、自分の文体をより強固なものにすること、おおむねそれしか考えてないです」(p.120)と断言している。
僕にとっては文章がすべてなんです。物語の仕掛けとか登場人物とか構造とか、小説にはもちろんいろいろ要素がありますけど、結局のところ最後は文章に帰結します。文章が変われば、新しくなれば、あるいは進化していけば、たとえ同じことを何度繰り返し書こうが、それは新しい物語になります。文章さえ変わり続けていけば、作家は何も恐れることはない。
『みみずくは黄昏に飛び立つ』p.189
これは本当にそうだと、個人的には思っている。どんな内容であれ、文章が素晴らしければついつい読んでしまう。物語にとんでも展開がなくたって、キャラクターが個性的でなくたって、文章が美味ければ面白くなるのである。ゆえに、何でもない日常のやりとりが面白いと感じる本に出合うたびに、「最っ高……」と呟いてしまう……
村上作品の文章がやはりこだわって作られているものであると、改めて知ることができて本当に良かった。
フェミニズムに対する回答
最後に、ちょっとセンシティブな話題について。私は村上春樹作品のファンではあるが、ここ数年、何となく読むのが難しくなっていたことがあった。なぜなら、フェミニズムやジェンダーについてあれこれと学んでいく中で、ほんの少し、作品に違和感を覚えるようになってしまったからだ。
そんな中、川上さんがフェミニズムの視点について切り込んでくれていたのが、とてもありがたかった。彼女は自分が村上作品のファンであることを前提としつつ、作品内で「女性というものが巫女的な扱われる、巫女的な役割を担わされる」「女の人が性的な役割を全うしていくだけの存在になってしまうことが多い」と言われていることを指摘していた。
例えば女友だちには、「あなたは村上春樹作品をすごく好きだけど、そこんとこ、どういうふうに折り合いをつけているの?」と聞かれることがよくあります。村上さんの小説に出てくる女性について、足がちょっと止まってしまうところがあると。それは男女関係なく、抵抗感を感じる人がいるんです。
『みみずくは黄昏に飛びたつ』p.245
これに対して、村上さんもまた、真摯に回答している。彼は基本的に「自我的なものとはできるだけ関わらないようにしている」といい、そうした構図は「意識していない」という。
男性であれ女性であれ、その人物がどのように世界と関わっているかということ、つまりそのインターフェイス(接面)みたいなものが主に問題になってくるのであって、その存在自体の意味とか、重みとか、方向性とか、そういうことはむしろ書きすぎないように意識しています。
『みみずくは黄昏に飛びたつ』p.247
正直に言ってしまうと、「うーん、まあ、そうだろうなあ」という感じ。予想通り、村上さんはジェンダー的視点を意識していなかったし、作品のキャラクターたちは少し浮世離れしたような人たちばかりだから、まさか自分たちが現実の社会課題と絡めて語られているなんて思いもしないだろう。私も違和感はあるけれど、批判したいのかと言われればちょっと違う気がしている。
その一方で、「この違和感はおそらく、村上さんにはわからないだろうなあ」とも思ってしまった。それは別に悪いと言いたいわけではなくて、私たち女性の多くが感じていることは、村上さんの生活環境や考え方の中にはおそらくないものなのだろうなと思うからだ。この溝、難しいなあ……
ただ、村上さんが改めて言葉にしていたのは、私にとってかなり重要だった。川上さんも「今のお話はわたしにとって、とても大事なこと」(p.249)とおっしゃっていて、心底頷いた。
本書は、私が今村上作品に思うこと、聞いてみたいことのすべてが詰まっていた。ほかの質問もユニークで、ついつい何度も読み込んでしまっている。






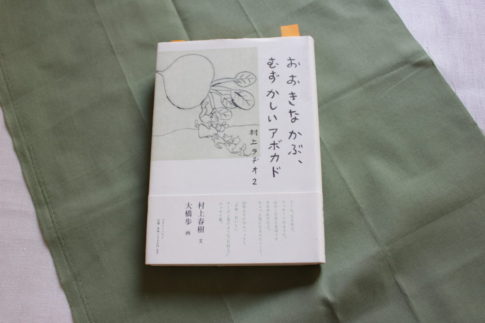












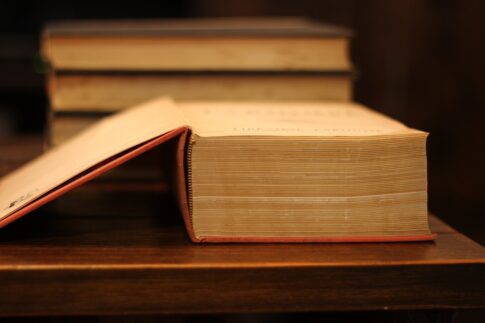



















コメントを残す