雑誌で紹介されているのを見つけて関心を持ち、読み始めた中島らもさんの『今夜、すべてのバーで』。読んでいる途中から、「なんだかこれは、すごい本だぞ……」と惹かれていき、読み終えた頃には出合ったことに感謝したくなった。
ふだんの本選びではもしかしたら見つけられなかったかもしれず、本当にラッキーである。静かな文章と、じわじわと進んでいく物語の展開が苦しくも引き込まれていく。
依存症の正体を多面的に描く作品
本作は、アルコール依存症になってしまった人々がその症状に悩まされ、苦しみ、ときに逃げながらも闘う記録を物語にしている。淡々とフラットに綴られた文章ゆえに、その惨状がリアルに響く。
アルコールにふりまわされる人々の様子がかなり詳細に描かれるほか、実際の文献もたくさん登場し、依存症の問題が多面的に示されている。何かしらの依存症に苦しむ人が登場するフィクションは数多くあるが、ここまで調べ抜いて書いていることに驚いた。

特に読んでいて苦しかったのは、主人公の容(いるる)が依存症に陥っていく過程であった。ただお酒が好き、というだけで依存症になるわけではない。
会社員からフリーランスに転向した容は、時間に縛られなくなり生活習慣が乱れていく。
そしてストレスのあまりにお酒を飲む生活を始め、どんどん胃が食事を受け付けなくなり、次第に「もはや、喉を通るもので、カロリーのあるものといえばアルコールだけ」(p.68)という状態になってしまう。
さらに言えば、容はウイスキーを飲みながらアルコール依存症の資料を読みあさっている。だから、アルコール依存症がどんなに恐ろしいものかも把握している。
それでも、依存症になってしまうのである。医師に「それだけアル中について知識をあさっておいて、アル中になったってのか」(p.73)と皮肉を言われるシーンは、笑えるどころか胸が痛くなる。
依存とまわりの人々と
依存症は家族や友人や、まわりの人にも影響を及ぼす。身のまわりの人たちの様子も多く出てくるが、最も印象的だったのは、老夫婦の話だった。
容と同じ病室にいる「吉田老」は妻に果物を差し入れてもらっている。彼は妻に感謝ひとつせずに怒鳴り散らすも、妻はのらりくらりと交わしている。容はそんな彼らを最初は微笑ましい夫婦だとみていたが、ふいに妻の「押さえきれない喜び」に気付く。
婆さんは、いまやじっくりと復讐を楽しんでいるのだった。愚鈍を装って、傲慢な夫の神経に、一本一本細い針を突き立てている。ののしられ、婢(はしため)あつかいされ続けたこの半世紀の間、婆さんはじっとこの日を待ち続けて耐えてきたのだろう。いまや、吉田老に残された武器は、どなり慣れた口だけだ。それも所詮は空砲だ。婆さんはいま、案山子の正体を知ったカラスになって、じわじわと一本足の吉田老に近づいていくのだった。
『今夜、すべてのバーで』p.118

夫婦のやりとりの真意に気付いたとき、そのどうしようもない闇に呑み込まれそうになる。吉田老には確かに同情するが、妻の長年の我慢はきっと、何にも代えられないほどの苦しみであったはずだから。
ただ、個人的にはこのシーンの文章が奇しくも、一番魅力的であった。静かに恐ろしく、それこそじわじわと追い詰められていくような感覚があった。
「依存」の本質はどこにあるのか
私は重度の依存症は、今のところないと思われる。スマホは怪しいなと思ったが、最近スマホを忘れて出かけてしまったり、朝からずっと寝室に放置していたり、というようなことがあり、「あんまり必要としてないんだな」とぼんやり思ったばかりである。
ただ、「依存症にはならない」とは、全く思わない。読んでいて、どうも他人事ではないというか、自分かあるいは周りの人なのか、何らかのきっかけさえあれば、依存症になり得るだろうなと考えたからである。

もちろんフィクションであるし、これだけが現実というわけでもない。しかし、生活の中には、容のようなストレスゆえの依存も確かに存在する。物語内に登場した「人間の“依存”ってことの本質がわからないと、アル中はわからない」(p.237)という言葉が、かなり心に残っている。
ちょうど今年は、ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書』を読んだばかり。同書もアルコール依存症にまつわる切実な内容が描かれていたので、より深く考えることとなった。
『今夜、すべてのバーで』、内容も文章も、ものすごい小説だった。読み終えてタイトルの意味を知ったとき、すべてが腑に落ちて、ぞわっとしたし、苦しくもあったし、それでいながら、その儚さを美しいとも思ってしまった。












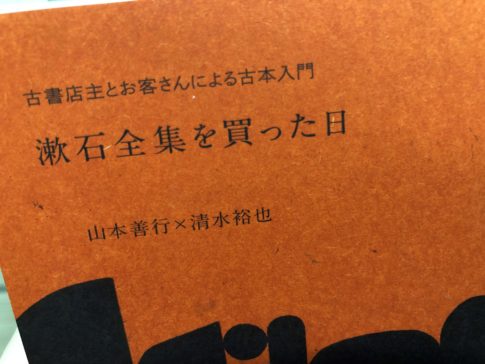


















コメントを残す