『ドリアン・グレイの画像(肖像)』に登場する美しい少年、ドリアン・グレイは無邪気で純粋で、それゆえに残酷さがある。無邪気さと残酷さは紙一重だなと感じる。
また、美しさに取りつかれる様、人々が外見によって善悪を判断する様が描かれており、ルッキズムへの批判があるようにも感じ取れた。
奇想天外なあらすじと感じるルッキズムへの批判
ドリアン・グレイの美貌は、多くの人を魅了し、虜にする。その魅力に取りつかれた一人、画家のバジル・ホールワードは、ドリアンの肖像画を描き、彼の美しさを絵に収めた。
ところが、あまりに美しいその肖像に、ドリアンは落胆する。なぜなら自分は年を取っていくのに、肖像画は一生、美しさを保ち続けるからだ。
これが逆でさえあったなら! いつまでも若さを失わずにいるのがぼくで、年をとっていくのがこの絵のほうだったなら! そのためなら――そうなるものなら――ぼく、いくらだって出す! そうだ、出さないものなんてこの世にあるものか! そのためならたましいだってくれてやる!
『ドリアン・グレイの画像』p.49~50
ありもしない空想のはずだったが、これが現実になる。ドリアンが罪を犯すたびに顔をゆがめ、年を重ねていく絵と、一切の美しさを損なわないドリアン自身。二つの対比が、物語のキーワードとなっていく。

ドリアンは無邪気で純粋な少年であるが、罪も加齢もすべて絵が引き受けてしまうから、彼自身はまったく成長せず、良くも悪くもそのままに生き続ける。それは一時的には本人に喜びをもたらすかもしれないが、長期的に見てとても有益なこととは思えない。見た目の美しさだけに囚われ続け、学ばず、内面の成長もできないからだ。彼の人生の行く末を見ても、明らかである。
「美しさ」に関する記述は、物語のあちこちで現れる。例えば、ドリアンは美しい女優・シビルに一目ぼれして恋に落ち、結婚をも意識するようになるが、いざ舞台を観に行った際、彼女の女優としての実力のなさにひどくがっかりしてしまう。「顔だけきれいな三流女優じゃないか」(p.150)と勝手に判断し、彼女と無理やり別れを告げる。それを受け、シビルはショックのあまりに死んでしまう。彼の安易な外見による判断が、彼女を不幸に陥れたのである。
あるいは罪の意識に耐えられず、街で出会った娘に「自分は悪人だよ」と打ち明ける。ところが娘はドリアンを見て笑い、「悪人というのはきまって老いぼれでとても醜いはずですわ」(p.362)などと答える。なんて軽薄な価値基準なんだ……でも、珍しい価値観とは言えないのが悲しい。
物語内では、犯罪は顔に出るとか、美しい人は純粋で魅力的であるとか、外見による決めつけがそこかしこで見かけられる。しかし実際にドリアンは罪を多く犯しながら、絵のおかげで美しさを保ち続けられている「悪人」ともいえる存在だ。
見た目で判断しきってしまう「ルッキズム」への強烈な批判が、描かれているように感じる。
無邪気な心に宿る残酷さ
『ドリアン・グレイ』を読んでいてもう一つ感じたのが、無邪気さに宿る残酷性である。ドリアン・グレイは物語内でいくつもの罪を犯すが、どれも「悪意に満ちている」とは言い切れず、そこに切なさがある。彼は素直に、自分の思った通りに行動してしまう。それがどれだけ、浅はかであっても。
友人である画家のバジルのことも、初めはしょっちゅう会いに行って大切にしていたが、ヘンリー卿と親しくなってからは途端に彼との交流を減らしていく。ヘンリー卿にバジルについて聞かれたシーンでは、あっさりと次のように述べる。
バジルね! ここ一週間も会ってないや。ぼくもひどい男だ、わざわざ自分でデザインした、とてもすばらしい額縁にぼくの肖像を入れて送ってくれたのに、それに、あの絵はぼくよりまるひと月も若いので少々ねたましい気もするけど、やっぱりうれしいにはうれしいんでね。そうだな、あなたからも知らせてもらったほうがいい。ひとりでは会いたくないや。ぼくの気にさわることばかりいうから。もっともらしい忠告するんだ。
『ドリアン・グレイの画像』p.99
ドリアンは一時期は反省するものの、結局元に戻って人に対して冷たい態度を取り、素行の悪い友人と関係を結び自分勝手な行動をとり続ける。それはやはり、絵が一手に、彼の罪を引き受け続けてしまうからかもしれない。
どんなにひどい行いをしても、醜くなるのは絵である。だからこそ「どんなことでも話題にさえしなきゃあ、起こらなかったも同然なんだ」(p.184)と言ってのけてしまう。そんな彼にバジルはがっかりし、「きみは心も、憐みもないような話しぶりだ」(p.185)と告げる。
憐みを感じるための時間は、ドリアンには存在しない。何でも自分の思い通りにしようとする、ある種無垢な心の中に慈しみを育てるにはやはり、考える時間や自分の罪を受け入れて反省する時間がある程度必要になるはずだ。それを持てないドリアンは、無垢と隣り合わせの残酷性をいつまでも心に秘めていなければならなくなるのだろう。
「正しい人物」は存在しないような気がする
では、バジルがすべて正しいのか? と言われれば、そんなことはないような気がする。バジルは確かに実直で思いやりのある存在だが、最初にドリアンの美貌を褒めたたえおだてさせたのは彼だ。また、常にもっともなことを言っているように見えるけれど、どこか理想主義で、現実はそれだけではうまくいかないだろうなと思わされることも多々ある。
一方、無垢なドリアンを支配するヘンリー卿は一見悪の役回りにも見えるが、彼がドリアンを悪の道へ導いたとは言いがたい気もする。
ヘンリー卿は決して素晴らしい人物とは言い切れないものの、世渡り上手で飄々としている印象もあり、それゆえ悪行を「非効率なもの」として捉えている。「犯罪ってものはもっぱら下層階級に属するしろものなんだ」(p.352)「食後の話題にできないようなことはしないにかぎる」(p.352)と断言する。そんな彼が、次々と浅はかな罪を犯し続けるドリアンに強く影響していると言えるかは、難しい。

ただ、ヘンリー卿とドリアン・グレイの関係は『17歳の肖像』を思い出す。ドリアン・グレイのような無垢な少年には、ヘンリー卿の世を上手に渡っていくさまがあまりに魅力的に映りすぎる。ゆえにその表面的なところばかりをまねてしまい、ある意味では影響を受けて、薄っぺらい人物像になっていってしまったのではないかと考える。
ドリアンが犯した罪を批判することはできる。しかしその一方で、ほかの登場人物が正しい、という判断はできない。それぞれに長所や短所があり、正しさや間違い、善悪が交じり合っている。そして現実も確かに、そうなのだろう。私たちは自分が正しいと思いすぎず、反省をしながらも、間違いと感じたことを批判していく必要があるのだ。それはとっても、とっても、難しいことだけれど……
ちなみにあとがきにおいて、影響を受けたかもしれない作品として『ジキル博士とハイド氏』が紹介されており、非常に納得した。絵画のドリアンと実物のドリアンは二重人格とも言えるのかもしれない。



























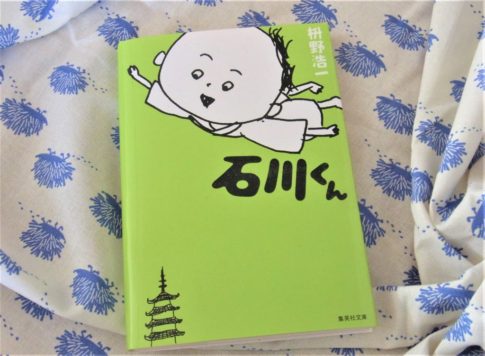





コメントを残す