帰り道、無性におなかがすいて「もうこれは家まで耐えられない」などと思い、コンビニでおにぎりを購入した。家に着くまでの間に、通りすがりの人に見られ、ちょっと恥ずかしい思いをしながら唐揚げのおにぎりをかじった。
幸せである。
私は、たぶんおにぎりが結構好きだ。たぶん、というのは「おにぎり好き」を公言するほどアイデンティティとして持ち合わせてはいないが、日常の節目節目でおにぎりを食べているからだ。もはや生活の一部のような存在である。
そんなおにぎりは、私だけでなく多くの人の生活に溶け込んでいる。たびたびおにぎりについての考察やエピソードを見かけるのは、偶然ではないはずだ。今回はおにぎりについて、好きなエピソードや考察をまとめておくことにする。
外国人に受け入れがたい、米を握る文化
お米はアジアや中東系の文化だけど、おにぎりは日本の特殊な文化の一つといえる。韓国は海苔巻きの文化があるけど、おにぎりはない。
「米を握る」という行為は、外国人からするととても不思議な行為らしい。
以前に『「おにぎり」のイノベーション』に参加したことがあったのだけれど、その際に中国でおにぎりの握り方をレクチャーしたところ、握る前に手を水にぬらすことを知らないので、手がべとべとになってしまう人が多かった、という話を聞いた。
たしかに、お米を握るなんてしないのであれば、手にひっつく発想そのものがないのは当たり前だ。

さらに、ヤマザキマリさんのエッセイ『パスタ嫌い』には、イタリアの電車の中でおにぎりを食べて驚かれたというエピソードが綴られている。
ところが、このおにぎりを食べ始めた途端、コンパートメントの中が異様な空気に包まれた。海苔から漂うイタリア人には嗅ぎ慣れていないだろう独特な磯臭さのせいもあるのだろうが、彼らには私がむしゃむしゃ頬張っているものが何なのか、一見しただけではわからない様子だった。私の向かいのシートには就学前の小さな男の子と、その隣には彼のお母さんが座っていた。目を細めてじっと私の食べているものを見つめていた男の子が、小さい声(と言っても聞こえる)で、「ママ、あの人子どものアタマみたいなもの食べてるよ……」と恐る恐る呟いた。
『パスタぎらい』ヤマザキマリ
子どものアタマ、のくだりに笑ってしまった。この後ヤマザキさんはまわりにおにぎりについて説明して、話がひとしきり盛り上がったようだった。
おにぎりに外国人が驚く、というエピソードは映画「かもめ食堂」も思い浮かぶ。小林聡美さん演じるサチエさんは、フィンランドで自身が経営するかもめ食堂のメニューにおにぎりを用意するものの、なかなか頼まれない。
しかし、日本人のお客さんであるマサコさんがおにぎりを注文して食べていると、フィンランド人のお客さんたちが、興味深そうにその姿を見つめる。見たことのないおにぎりという料理に驚きを隠せないような表情だった。
サチエさんが「おにぎりは日本のソウルフード」といって笑うシーンがとてもいい。
寿司やすき焼きなどの高級料理はジャパニーズキュイジーヌとしてバンバン世界に飛び立っていくのだろうが、おにぎりのような庶民食はなかなか広まって行きづらいのかもしれない。
日本のお米はおにぎりに向いている
日本食糧新聞社『ご当地弁当惣菜ガイド』では、伝承料理研究家である奥村彪生氏による「食文化としての弁当の歴史」についてのコラムが掲載されている。その中に「にぎり飯」の話があった。
コラムによれば、お弁当自体は中国や台湾にもある。お米も入っているらしいのだが、ご飯もおかずも温かいことが特徴なのだという。使われているインディカ米や長粒種は、冷めるとあまり美味しくないからだそうだ。
一方日本のお米はジャポニカ米と呼ばれる種類だが、これは粘り気があり、冷めても美味しいのが魅力。そしてこの粘りが“握る”という行為に大変役立っているという。日本でおにぎりが発展したのは、このジャポニカ米の特徴が影響しているのかもしれない。
ちなみにおにぎりの文化は、奈良時代に始まっている。風土記に「握飯(にぎりいい)」と記載があるのだから、本当である。こんなに昔からあるなんて、本当にソウルフードといっても過言ではないだろう。

おにぎりの形は三角だけではない
子どもの頃、遠足に持って行ったお弁当のなかに入っていたおにぎりは俵型だった。違和感を抱いたことはなかったが、東京に住んでからは俵型のおにぎりなど見たことがない。三角が王道であるといつのまにか刷り込まれ続けている。
しかし全国津々浦々、見渡してみればいろいろなおにぎりがある。俵型と三角だけにも限らない。先述の『ご当地弁当惣菜ガイド』内コラム「食文化としての弁当の歴史」では、おにぎりの形についても言及されていた。
チェーン展開しているコンビニエンスストアでは三角形が多くを占めていますが、地方によりその好みがあり、東北は丸みを帯びた円板型、関東は三角、京都は卵型、大阪は俵型、九州はボール型です。なお、熊野地方では古漬の高菜漬けの葉で包んだ(茎は細かく刻んで削り鰹節とあえて具として中に入れる)日張り飯は、その昔、山仕事に行く職人さんの弁当でした
『ご当地弁当惣菜ガイド』 奥村彪生「食文化としての弁当の歴史」
形にしろ味にしろ、おにぎりの可能性はまだまだ無限大なのである。
進化するコンビニおにぎりの不思議
自宅で握るものだけがおにぎりではない。コンビニで販売されているおにぎりが好きな人も多いだろう。家で握るものとはまた、違った魅力がある。味も家では作らないであろうものが多い。焼肉が入っていたり、鮪が入っていたりして具を選べるのも楽しい。
穂村弘さんの『君がいない夜のごはん』では、コンビニおにぎりの進化について書かれている。
ある年配の作家さんから、初めて砂糖を食べたときの話を聞いた穂村さんは、その衝撃的な経験をうらやましく感じたという。そこで自分もそういう衝撃的な経験をしていないかと考えたところ、コンビニおにぎりの進化に思い当たった。
ところがコンビニおにぎりの進化はすごいと感じるものの、砂糖ほどに衝撃はない。
「コンビニおにぎりが原始的で苦労した」人々の平成期の努力によって、今では全国民がこんなにおいしいコンビニおにぎりを食べられるようになった、という感覚は希薄だ。私が生きてきた時期は、むしろその時代にぴったりと重なっている筈なのに実感がないのだ。
自分と関係のないところで、いつのまにか自動的にコンビニおにぎりはおいしくなっていった。コンビニサンドイッチやコンビニ冷やし中華も勝手に進化していた。
私はただ、お、開けやすいじゃん、とか、なんか御飯がふっくらしたな、とか思っただけだ。
『君がいない夜のごはん』「コンビニおにぎりの進化」穂村 弘
確かに、ずいぶんとコンビニおにぎりはおいしくなったし、開けやすくなったし、中学生の頃に買ったあのおにぎりは、開けづらくてあんまりおいしくなかった気がしてきた。
いつのまにか進化している。この進化がなくては、今大人になってもこんなふうにおにぎりなんて買わなかったに違いない。あまりに日常にありすぎて、自然に受け入れてしまっているのだ。
おにぎらずは、おにぎりの仲間か?
仮におにぎりの反対語があるとすれば、「おにぎらず」が正解なのだろうか。
最近、おにぎらずはかなり市民権を得ているように思う。具材をつつましやかにひっそりと隠すおにぎりと違い、おにぎらずはその具材の魅力を最大限にアピールできる外見をしている。どちらかといえばサンドイッチに近い印象だ。
登場した当時(もう何年前なのかわからないが)、これはもう新しすぎてわからない、と混乱してしまったが、今はすっかり受け入れられている。具材が見えるのはわかりやすいし、鮮やかだし、包み込まない方が入る具材もある。
たとえば、沖縄のポークたまごおにぎりはポークと卵焼きを包むので、どうしても具材がはみ出る仕様になるし、おにぎらずのスタイルの方が向いている。
海苔の名店「浜乙女」さんでさえもおにぎらずのページを作っているくらいだから、もう和食の定番メニューの一つと言えるのかもしれない。
とはいえ、なんとなくおにぎりの対義語みたいに見えるおにぎらずは果たしておにぎりの仲間と言っていいのだろうか……いまだにちょっと疑問ではある。
おにぎりはやはり私だけでなく、多くの人の心に自然と根づいている。まるで長年連れ添った夫婦のように、あるいは何十年と付き合いのある友人のように、身近で温かい食べ物だと言えるだろう。






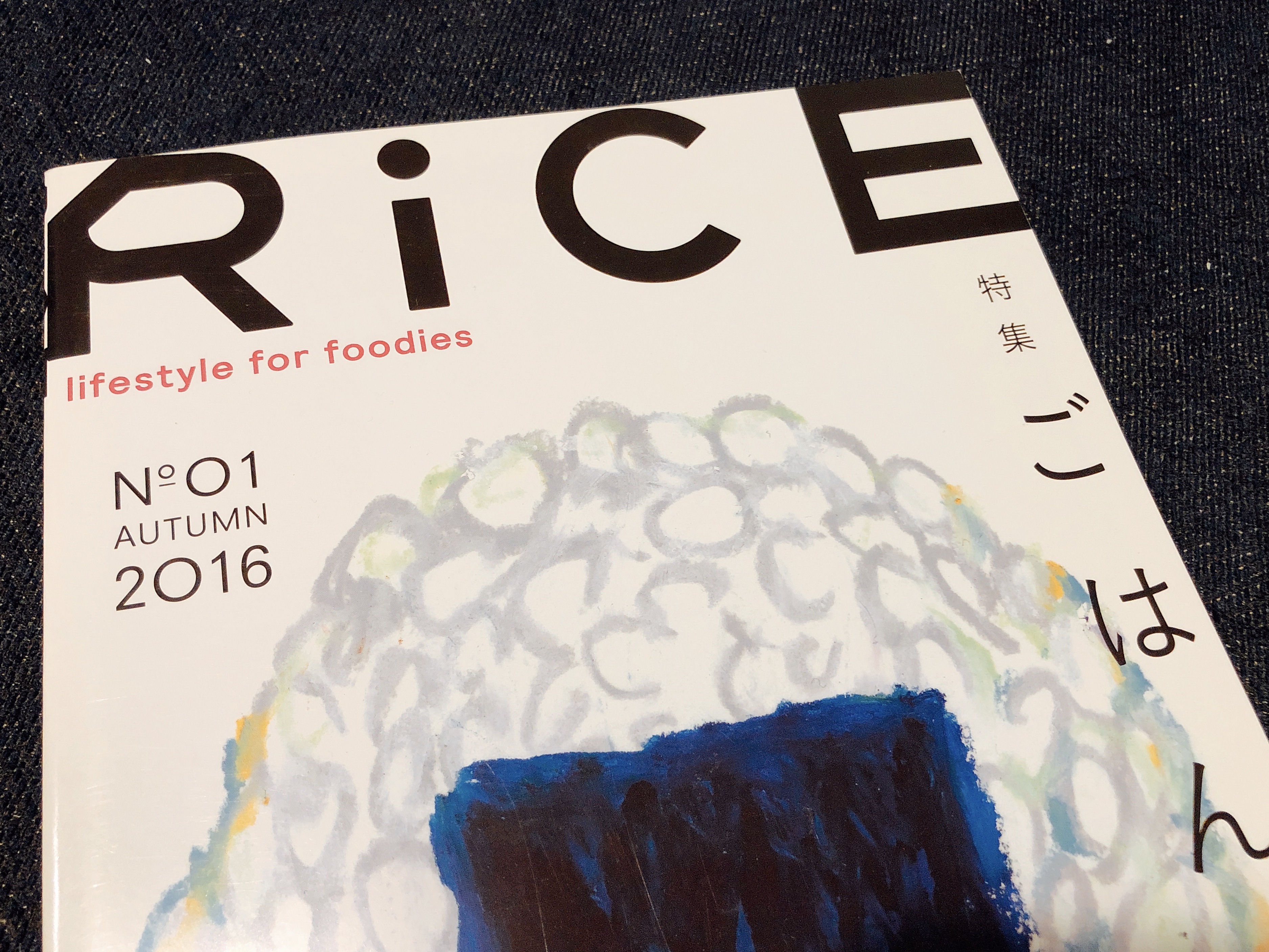





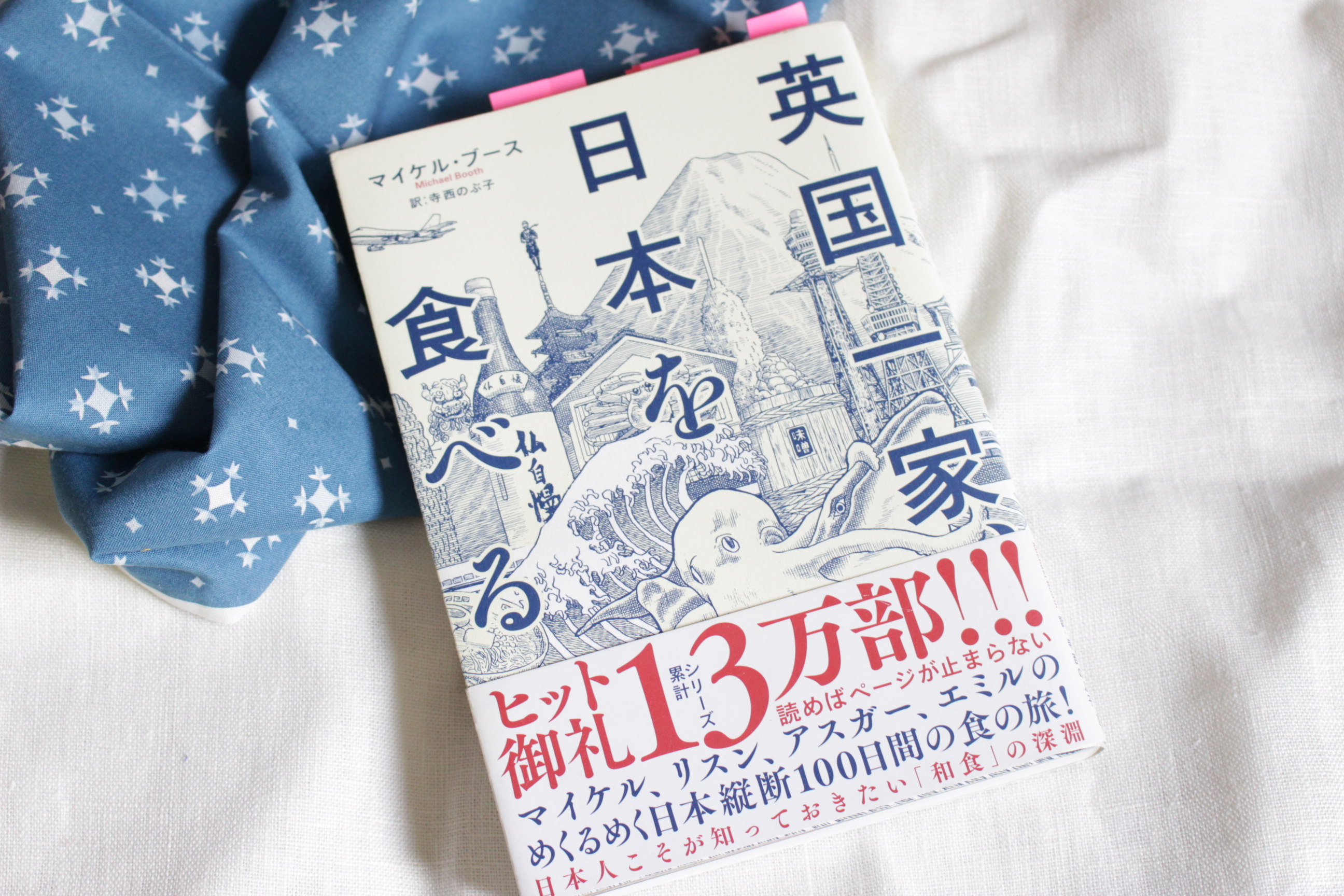










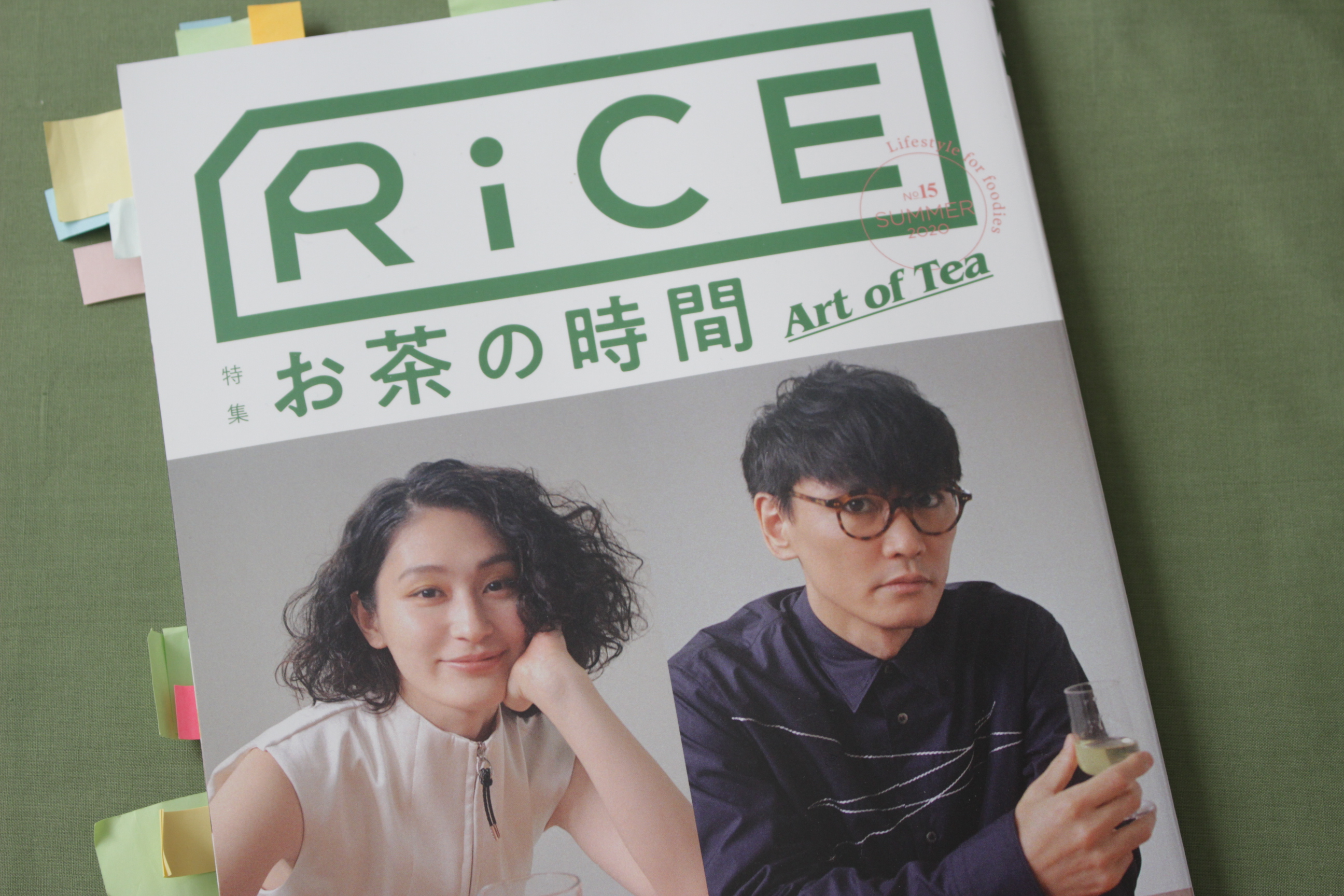




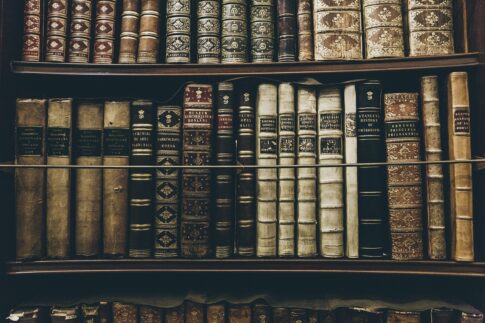



コメントを残す