クラリッサ(=ダロウェイ夫人)を取り巻く1日を記した小説『ダロウェイ夫人』。彼女がパーティを開くために準備をする中で、自分の暮らしや人生やパートナーについて思いを巡らせ、自分なりの価値観を示していく。
また、クラリッサが主人公ではあるものの、「意識の流れ」の手法によって、さまざまなキャラクターたちの思案が蝶のように舞う。それゆえに物語に何重もの厚みがあり、たった1日の出来事でありながらも、とんでもなく壮大な話を読み終わったかのような達成感があった。
相手とわかり合えない苦しみが、じわじわと染みる
同作では、各キャラクターの心の声が終始飛び回っている。それゆえに私たち読者は、しょっちゅう彼らの「わかり合えなさ」に直面することになる。例えば、クラリッサと元恋人のピーターは表面には見せないながら、心中で互いに過去を思い出し、現在の姿を勝手気ままに評価する。
クラリッサがピーターに対し「わたしをいらつかせるのは、この人のばかげた破れかぶれ、他人の感情の思いやりのなさ。いまもそう、これまでもずっとそう」(p.85)と判断している一方で、ピーターは「クラリッサはなんだかきつくなった。おまけにおセンチの気味も増した」(p.89)と考えていたりする。同じことを思い出し、考えるにしても、二人の気持ちはまったく異なっていて、わかり合えない難しさや苦しさをじわじわと感じる。

同時進行で繰り広げられる、セプティマスとその妻・レーツィアのやり取りも同様だ。セプティマスは自分に感情がないことを恐れ、パニックになり、生きづらさを感じている。だが、それを妻にわかってもらえず、「妻は邪魔ばかりする」と苦しむ。
一方でレーツィアは、セプティマスが何を考えているかわからずに不安を抱え、「もう堪えられない」と感じている。
これならむしろ死んでくれた方がまし。あんなに何かを見つめながらわたしには目もくれず、何もかもめちゃくちゃにする人なんて、もう一緒に座っていられない。空も気もいや。おもちゃの車を引き、笛を吹き、転びながら遊んで居る子供もいや。何もかもいや。夫は自殺せず、わたしには話せる人がいない。
『ダロウェイ夫人』p.45
「妻が泣いているのに、ぼくは何も感じられない。底知れない静寂と絶望のなかで妻がしゃくり上げるたび、夫は一歩ずつ奈落に下りていった」(p.159)という部分に、最も苦しくなった。このわかり合えなさは、「話し合えばわかる」とか「いつかわかり合える」とか、そういう前向きな言葉たちからはかけ離れている。「どうしようもなさ」を突きつけられているが、そのどうしようもなさは確かに私も感じたことがあって、「わかる」と思ってしまうのが辛い。
「意識の流れ」と圧巻のパーティーシーン
『ダロウェイ夫人』の物語の主軸は「パーティー」にある。クラリッサが準備を行い、実際にパーティーを開催するまでの1日の様子を描いているからだ。彼女は誰に何を思われようと「わたしはただ生きたいだけ」といい、「だからパーティーを開くの」と宣言する。生きづらさやわかり合えなさを感じ続ける彼女が自由になれる瞬間のようで、清々しい気持になる。
私は本作の中で、最後のパーティーシーンが一番好きだ。次々とパーティの参加者が現れて、それぞれが会話し、彼らの感情が流れるように吐露されていく。
それはまるで、大勢のパーティに自分が放り込まれたような感覚。本を読んでいるだけなのに、まわりをさまざまな人たちに取り囲まれているような気持ちになる。あちらこちらで聞こえてくる会話や人の様子を360℃、パノラマのようにして覗いている気分である。
これは先述の「意識の流れ」の手法が大きく影響しているのだろう。何度読んでも、圧倒される。

恋愛と結婚と女性の分断
もう一つ、本作で印象的であるのは、この時代に生きる女性たちの生きづらさと分断である。と言っても、悲しいかな、現代の日本とあまり変わらないのでは? と思われる風景もあって辛い。ジェンダー観は進化しているはずだけれど、変わらず残り続けてるものもあるのだなと実感する。
クラリッサは結婚し、子どもを生んだことによって、自分を見失っているような描写があちこちに見られる。クラリッサから「ダロウェイ夫人」となったとき、「自分が透明になったような奇妙な感覚にとらわれた」という。
見えず、知られず、もう結婚することもなく、子を生むこともない。ポンド通りの意外なほどの――でも、なんだか厳かな――行進に混じり、ついていくだけ。ダロウェイ夫人というこの感覚。もうクラリッサですらなく、リチャード・ダロウェイの妻というこの感覚。
『ダロウェイ夫人』p.24
誰かの妻と認識されることで、自分自身の存在が薄れたように思ってしまう感覚は、珍しくないように思う。これは日本でもあることで、だからこそ「選択的夫婦別姓制度」の重要性が今問われているわけである。

一方、裕福な既婚者であるクラリッサを軽蔑する、ドリス・キルマンの存在も気にかかる。彼女は独身で、クラリッサの娘・エリザベスの家庭教師を勤め、自分の手で働いて生きている。それゆえに、優雅に暮らしているように見えるクラリッサが気に入らない。
こんな贅沢の中にいて、どうして社会の改善を目指す気になどなれるの。いつまでもソファに寝転んでないで(「母は休んでいます」とエリザベスが言っていた)工場に行きなさいよ、カウンターの後ろに立ちなさいよー―あんたもマダム連中も。
『ダロウェイ夫人』p.217
キルマン氏はクラリッサを軽蔑し、バカにしており、「打ち勝ちたい」と考えている。ところがあるとき、クラリッサの隣に並んだ瞬間、ふと「自分がどう見えるか」を気にしてしまい、おまけにクラリッサに笑われ、打ち負かされて泣きだしそうになってしまう。
一見、キルマン氏とクラリッサの馬の合わない部分が露呈した、「女同士の戦い」のように思える。ただ私は、当時の社会的価値観に惑わされた結果の分断のように感じた。女同士の戦いと称されるものは往々にして、外部からの分断がきっかけとなっているように思う。クラリッサ=幸せな女、キルマン氏=不幸な女と社会が捉える限り、この分断は終わらないところが悲しい。
そんな中、エリザベスはクラリッサとキルマン氏の間に立つ存在として描かれている。二人の生き方を冷静に観察しながら、自分はどう生きるべきかを考える姿は頼もしい。特に、彼女が自分の夢について「わたしの世代は女にもすべての職業が開かれるってキルマン先生は言う。なら、お医者さんになろうかな。農場経営もいいな、動物もよく病気するから」(p.237)と語っているシーンは、未来が開けているような感じがして好きだった。ちゃんとなりたい仕事に就けたのだろうか……そうであってほしい。
ウルフ作品に潜む「ユーモア」のこと
『ダロウェイ夫人』を含むウルフ作品は、『かわいいウルフ』を読んで、彼女の作品たちの中にあるユーモアに気付いてから一層面白くなった。
クラリッサやセプティマスのセンシティブな一面や、女性の分断や生きづらさ、恋愛の繊細なやり取りは本作に欠かせないエッセンスだが、そのセンシティブさとユニークさが相まって不思議な魅力を作り出している。全体って気に笑えるけど笑えない、苦しいけど笑いがこぼれる、というような、フクザツさがあるのだ。特にピーターがナイフをいじるシーンやクラリッサを想うシーンは定期的に出てくるゆえに、おかしさと切なさが入り混じった。
ちなみに、解説にジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』の設定を意識しているとあり、なるほど……読んでいるときは気づかなかったが、確かにそうだ、と頷いたのだった。

























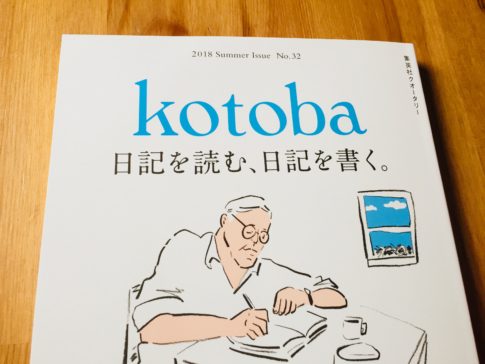









コメントを残す